目次
【1】六曜とは何か
1-1.最もポピュラーな開運情報です
六曜とは「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の六種類で表された暦注(その日の吉凶や運勢)の一つです。六輝(ろっき)とも呼ばれていますが、カレンダーや手帳を見れば普通に記載されているお馴染みのものです。

六曜とは暦を見るだけでわかる最もポピュラーな開運情報です、でもそれぞれの意味となるとどうでしょう。大安は吉、仏滅は凶くらいは知っていても、先勝や赤口となると多分わかりませんね。
1-2.暦注から「お日柄」を気にする文化や習慣
ただこの六曜のように暦注から「お日柄」を気にしたりゲンを担ぐ、といった習慣や文化は今でも私たちの生活に溶け込んでいます。
結婚式場など「大安」の日は人気であり、式場によっては費用もその分高く設定されていたりしますね。また「友引」の火葬は忌み嫌われていることから、多くの火葬場が友引を休館日としており告別式を行うことはできません。
【2】六曜が「差別」につながるのはなぜか
2-1.六曜入りカレンダー配布中止問題
しかし、その一方では誰もが「信じない」とは言いながらこういった「迷信」に従っていることに異を唱える声もあります。
六曜に限らず「占い」や「血液型」などは根拠や事実に基づかない意味づけである。また物事を正しく判断する力を奪う何ものでもないもの。そして科学的根拠に基づかない迷信や因習が、偏見や差別など人権問題につながる恐れがあるといった理由からです。

こういうった考えから、六曜を暦から排除・追放しようとする運動もあったのです。2016年大分県の佐伯市における「六曜入りカレンダー配布中止問題」などずいぶんと話題になりました。
何の根拠もない六曜が掲載されたカレンダーなどは公的な配布物としてふさわしくない、人権に配慮すべきであるといった声からです。もちろん「載せて何が悪い」といった問い合わせも相次いだそうですが。
2-2.それでも日取りが大事にされる理由
仏滅の日に結婚式をあげたり、友引の日に告別式を行っても何の問題はないはずです。しかし世間からは「非常識」といった目で見られることでしょう。
六曜などふだん気にされる方など少ないはずです。でも冠婚葬祭や開業・開店、また特別のイベントとなるとまだまだ「日取り」が重んじられているようです。

ここにあるのは「信じる・信じない」ということではなく、やはり縁起を担ぐこと、また長年続いている習慣や世間体を気にしてのことでしょうか。
もちろんこんな古い習慣など気にされない方も多いはずです。ただこうしたことが「偏見や差別を助長させるもの」といった見方もされていることもこの際知っておきましょう。
【3】六曜と仏教は関係ありません
3-1.仏滅の意味、「和漢三才図会」を見てみると
ちなみに六曜には「仏滅」といった日もあるのですが、仏教と六曜はまったく関係はありません!もちろん神道とも無関係です。ではなぜ仏様がでてくるのでしょうか。
「和漢三才図会(わかんさんさいずえ)」という江戸時代の中頃編纂された類書があります、類書とは百科事典のようなものです。この中に六曜のルーツともいえる「六壬時課(りくじんじか)」が紹介されており、ここでは吉凶の変化が「大安・留連・速喜・赤口・小吉・空亡」の順で表されています。
仏滅についてはこの空亡(くうぼう)が、
「空しく亡びる→物滅→仏滅」
と時代を追って変化したものといわれています、「当て字」ですね。後で触れますが現在使われている六曜は日本独自にアレンジされたものなのです。
【4】お坊さんの合コンは友引の前夜!その理由は
4-1.友引はお坊さんの定休日
また前述の通り「友引」の日は多くの火葬場がお休みです。この「文化」のおかげでお葬式が行われない事が多いこの日は、お坊さんにとって「定休日」のようなもの。お坊さんの飲み会や合コンは「お通夜」がないこの友引の前夜に行われていることが多いそうですね。会合や研修会が開かれる日もこの日が多いようです。
無関係とは言え六曜は仏教界にも影響を与えているわけです。

【5】六曜の伝来と人気の秘密
5-1.なぜ六種類なのか、「六行説」に由来します
六曜とはもとは古代中国で用いられていたものです。「小六壬(しょうりくじん)」や前述した「六壬時課」などと称され、おもに時刻の吉凶を占う手段でした。考案者は唐時代の暦学者である李淳風説が有力ですが、諸葛孔明が戦術法として編み出したといったものもあります。
ただいずれも真偽のほどは定かではありません。
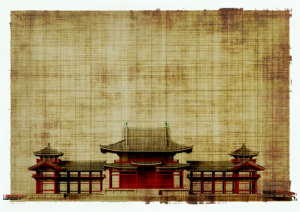
ではなぜ六種類なのか、これは古代中国における「六行説」に由来するそうです。東西南北と天地を合わせれば六つ、物事は六つに分類出来るといった自然哲学に基づかれているようです。ただこの説は五行説(五行思想)が優位になり廃れてしまいました。
ちなみに五行とは、物事は「火・水・木・金・土」の五つのものからなるという説です。
5-2.日本オリジナル!「選日法」としての六曜
そしてこの六曜が日本に伝来したのは鎌倉から室町時代といわれています。
ただ、時刻の吉凶など占う習慣がなかった日本では普及はしなかったようです。しかし江戸末期、この時刻占いに手を加え「選日法」として暦に掲載されたのです。するとたちまし人気を博し、庶民の間に爆発的に広がりを見せたのでした。
5-3.人気の秘密はこの二つ
このように私たちが暦で目にする六曜とは、本来の名称やしくみに手が加えられ、日本独自にアレンジされたものなのです。ではその人気の秘密とは何だったのでしょうか、これについてはよく言われているとおり、
- わかりやすさ
- 神秘性
この二つがあげられます。
5-4.わかりやすさと神秘性
六曜には吉凶が六種類しかありません、一見すると「たったこれだけで」と思われがちです。でもこの「わかりやすさ」が受けたのです。
世間が暦に求めたのはシンプルさや使い勝手のよさ、また娯楽性だったのでしょう。それから六曜はその並びに規則性があるのですが、独特のルールがあり不意にその順が途絶えます。
こういったことが当時の世間に神秘性や謎めいたものを感じさせたのです。
【6】明治の改暦で廃止された六曜ですが
6-1.世間の反感を招きました
しかし、そんな六曜も明治の改暦が行われた際、政府はこの六曜だけでなく暦注の吉凶占いを「迷信である!」として一切禁止、排除してしまいました。
しかしこの措置は世間の反感を招きました。六曜人気はその後も衰えることもなく、独自に六曜が掲載された民間暦が出版されるほどだったのです。六曜が本格的に広がりを見せたのは、この明治以降であるといわれています。
ちなみに政府による統制は、第二次大戦後に廃止されました。
6-2.六曜とは民俗信仰のようなもの
このような歴史を経て、六曜は現代にも脈々と受け継がれている「民俗信仰」のようなものです。
またそのルーツは遠い昔にありますが、歴史はまだまだ浅いものでもあります。「先勝」と書いてあっても「さきがち・せんしょう・さきかち」など読み方もはっきりしておらず、その解釈も明確に定まっていないのはそのためなのでしょう。
では次にそれぞれの意味について解説してみます。
【7】六曜の意味!その暗示するものとは
7-1.六曜とその意味一覧表
| 六曜 | 意味 |
|---|---|
| 先勝 ・せんがち ・せんしょう ・さきかち | 先んずれば勝ち!の通り「早ければ吉」です。とにかく後回しにせず、スピーディーな対応、すぐに行うことが運を呼び込む日です。午前が吉、正午と午後が凶です。 |
| 友引 ・ともびき ・ゆういん | 進まず引かず、勝負がつかない!といった意味です、どっちつかず・吉凶なしです。この日にお葬式などが行われない理由は「凶事に友を引く」など、災いが友にも及ぶといわれるからです。結婚式や開始・開業などは吉。午前と午後が吉、特に正午は凶につき要注意です。 |
| 先負 ・さきまけ ・せんぷ ・せんぶ | 先んずれば負け!先勝とは逆の意味の日です。勝負事や急ぎの用も焦りは禁物、万事慎重にかまえましょう。午前と正午が凶、午後が吉とされています。 |
| 仏滅 ・ぶつめつ | 仏様とは関係がないことは前述の通りです。ただ六曜の中においては大凶の日、引越しや開店などの新規事業は控えるべき一日です。またうっかりミスも心配です、しっかり気を引き締めていきましょう!午前・正午・午後すべて凶です。 |
| 大安 ・たいあん | 大吉!「おおいに安んずる」の意味、六曜の中ではもっともよい日、万事に吉です。この日に始めるものには「よい気」がつきその後も順調、祝い事にも最も適した日です。引越し・旅行・新規開店、特に結婚にはピッタリです。午前・正午・午後すべて吉です。 |
| 赤口 ・しゃっこう ・しゃっく ・じゃくじつ ・じゃっこう | 何をされるにも悪い一日です。特に祝い事については大凶とされていますが、火の元や刃物の扱いにも注意が必要です。正午だけが吉、午前と午後は凶とされています。 |
7-2.午前・正午・午後とは何時のことですか
たとえば先勝ならば「午前が吉、正午と午後が凶」ですが、それぞれ何時頃を指すのでしょうか。六曜における時間については
- 午前:0~11時
- 正午:11~13時
- 午後:13~24時
となります、ただこれはあくまでも六曜における時間です。
【8】六曜の並び順とその規則
8-1.カレンダーを見てみましょう
六曜の並び順は「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」が基本です。しかし曜日(月・火・水~)のように常に規則正しく繰り返されるものではありません。
たとえば2023年のカレンダーを例にとると、5月19日は友引ですが20日は仏滅になっています。友引の次は先負なのになぜ仏滅になっているのでしょう。
8-2.ポイントは旧暦です
この謎めいた順も六曜人気の一つなのですが、ここには旧暦を基準にした単純なルールがあります。というのは、旧暦の1日になると六曜の先頭が変わるのです。
- 旧暦1月1日:先勝より
- 旧暦2月1日:友引より
- 旧暦3月1日:先負より
- 旧暦4月1日:仏滅より
- 旧暦5月1日:大安より
- 旧暦6月1日:赤口より
そして7月1日からは再び先勝に戻り同様の順が繰り返されるのです。
例にあげた2023年5月20日の場合なら、この日が旧暦における4月1日に当たるため仏滅となるわけです。ちなみにこの年の場合では、1月22日(日曜日)が旧暦における1月1日なので先勝となっています。興味がある方は確認してみてください。
【9】六曜には計算式もあります
六曜は旧暦をもとに計算で求めることも可能です。ただ何も計算などしなくても暦やネットを見ればすぐわかることなのですが。ここでもポイントは旧暦の日付です。
9-1.6の倍数は「大安」です
たとえば旧暦の日付を合計した和が、6の倍数であれば「大安」です。
スポンサーリンク
2023年3月1日は大安です。
この日は旧暦において2月10日です。
2+10=12。
12は6の倍数、よって大安です。
このように、
(旧暦の月 + 旧暦の日付)
を6で割りその余りで判断できます。
・余り0:大安
・余り1:赤口
・余り2:先勝
・余り3:友引
・余り4:先負
・余り5:仏滅
2023年4月29日は赤口です。
この日は旧暦において3月10日です。
3+10=13
13÷6=2余り1
よって赤口です。
【10】六曜の活用方法とは
10-1.運気を呼び込みたければ「行動」がすべてです
最後にこの六曜の活用方法について考えてみましょう。まずは単純に雑学や一般常識のひとつとすること、また冠婚葬祭など日取り選びの習慣やマナーを知ることでしょうか。ただし運命を変えたり、運気を呼び込みたければ「行動」がすべてです。
だからこの六曜もその「きっかけやヒント」として利用するなら価値も「あり」ではないでしょうか。日程選びに限らずちょっとした選択肢の一つに加えてみたらいかがでしょう。頼るのでなく、あくまでも利用することがポイントですね。
あわせてどうぞ!
スポンサーリンク

























